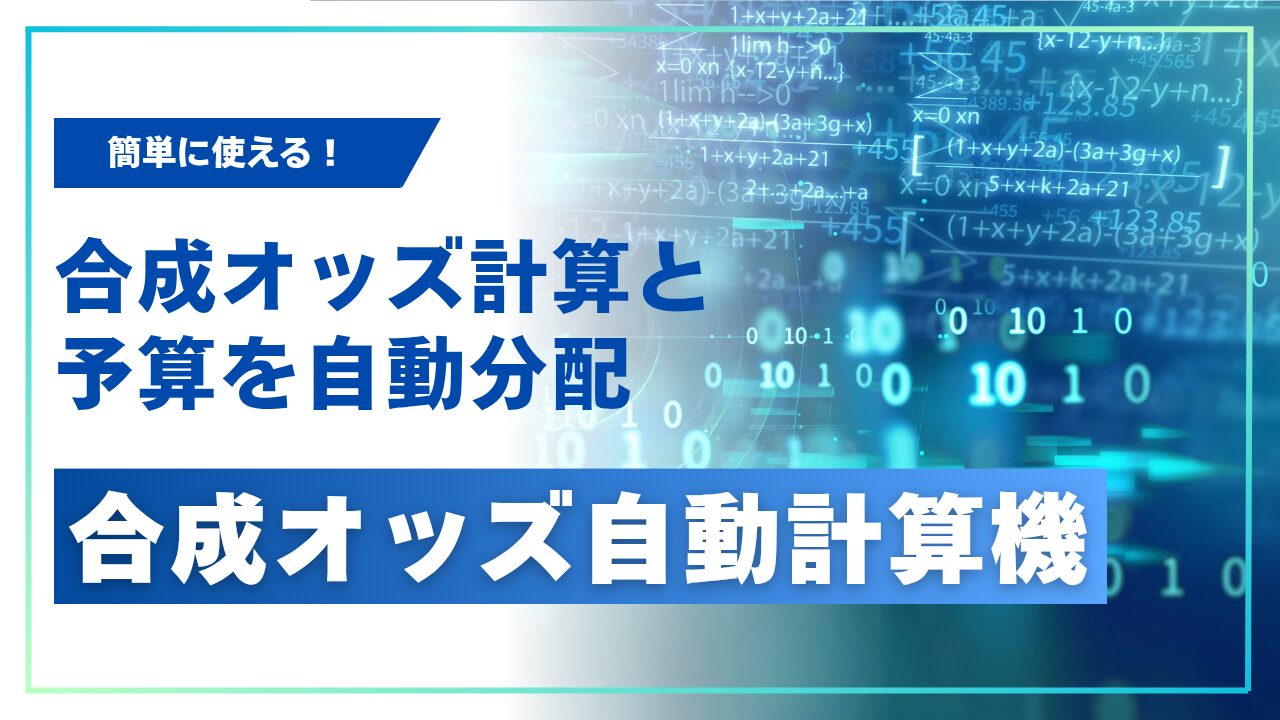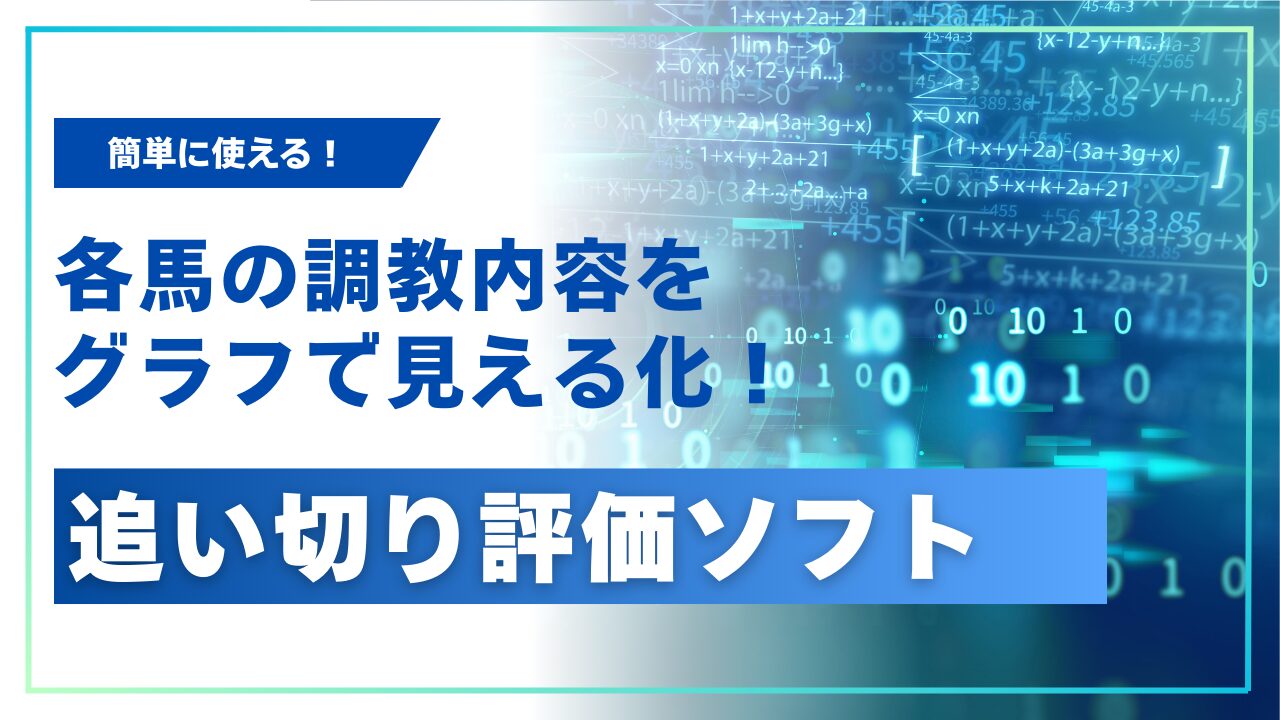【競馬レーティング完全ガイド】見方と活用法を解説!馬の強さを客観評価!

競馬の魅力は、単にレースの勝ち馬を当てるだけではありません。競走馬の血統、日々の調教、陣営の戦略、そして何よりも馬自身の持つ能力が複雑に絡み合います。この奥深い世界で、「レーティング」という指標は、競走馬の能力を客観的に評価し、異なるレースや国で走った馬たちを比較するための「共通言語」として非常に重要な役割を果たしています。
- 近年その圧倒的な強さで世界を驚かせたイクイノックスが叩き出した驚異的なレーティング
- 無敗の三冠を達成し多くのファンを魅了したディープインパクトが記録した数値
- 破天荒な強さで記憶に残るオルフェーヴルのような名馬たちが、国際的にどのような評価を受けていたのか
こうした具体的な数値を通して「名馬の強さ」を客観的に比較できるようになると、競馬観戦や分析がより深く、そして何倍も面白くなるはずです。
しかし、「レーティングってよく聞くけど、結局何なの?」「どうやって予想に活かせばいいの?」そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。そのままだと、いつまでも感覚頼みの予想から抜け出せず、回収率も上がらない可能性があります。
当サイトはデータ分析を重視し、皆様の回収率向上をサポートすることを目指しています。この記事では、レーティングの基本的な意味から、JRAや国際的なレーティングの種類、算出の仕組み、レースレベルの見方、そして競馬予想への活かし方まで、網羅的に学ぶことができます。
レーティングを正しく理解し活用することが、感覚的な予想から脱却し、データに基づいた競馬分析で回収率向上を目指すための重要な第一歩です。
レーティングの具体例:名馬たちの数値とその意味

まずは、競馬ファンなら誰もが知るような名馬たちが、実際にどれくらいのレーティングで評価されてきたのか、そしてその数値がどれほどの強さを示すのかを見てみましょう。具体的なイメージを掴むことで、この後の解説がより分かりやすくなるはずです。
歴史的名馬の最高レーティングとその背景
日本競馬の歴史を語る上で欠かせない名馬たちが記録した代表的なレーティングと、それが達成されたレース、そしてその数値が持つ意義について、各馬の輝かしいレース映像を思い浮かべながら見ていきましょう。
| 馬名 | 最高レーティング | 主な達成レース (年度) |
| イクイノックス | 135ポンド | ジャパンカップ (2023) |
| エルコンドルパサー | 134ポンド | 凱旋門賞 2着 (1999) |
| ジャスタウェイ | 130ポンド | ドバイデューティーフリー (2014) |
| オルフェーヴル | 129ポンド | 有馬記念 (2013) |
| ロードカナロア | 128ポンド | 香港スプリント (2013) |
| ディープインパクト | 127ポンド | 有馬記念 (2006) など |
| アーモンドアイ | 124ポンド | ジャパンC (2018, 2020) など |
イクイノックス 135ポンド
まずは、記憶に新しいイクイノックスです。2023年のジャパンカップで見せた圧倒的なパフォーマンスにより、135ポンドという驚異的なレーティングを獲得しました。これは日本調教馬としての歴代最高評価であり、この年の世界の競走馬ランキングでも堂々の年間第1位に輝いた、まさに歴史的な記録です。その圧巻の走りは、多くの競馬ファンの記憶に深く刻まれています。
エルコンドルパサー 134ポンド
続いては、日本競馬の悲願の一つである凱旋門賞に限りなく近づいた名馬、エルコンドルパサーです。1999年の凱旋門賞で2着と激走し、134ポンドという極めて高いレーティングを獲得しました。これは当時の日本調教馬としては破格の評価であり、日本馬が世界のトップレベルで互角以上に戦えることを証明した、歴史的な一戦として語り継がれています。
ジャスタウェイ 130ポンド
ジャスタウェイも忘れてはならない一頭です。2014年のドバイデューティーフリー(現在のドバイターフ)で見せた衝撃的なレースは、130ポンドのレーティングを獲得。これにより、同年の世界の競走馬ランキングで年間第1位の栄誉に輝きました。イクイノックスが登場するまで、日本調教馬として単独で世界の頂点に立ったその走りは、今なお鮮烈な印象を残します。
オルフェーヴル 129ポンド
次に、破天荒な強さと個性でファンを魅了したオルフェーヴルです。日本のクラシック三冠を達成し、凱旋門賞でも2年連続2着と世界を驚かせました。その中でも2013年の有馬記念で129ポンドという高いレーティングを記録しています。その圧倒的な強さを示す走りは、まさに伝説的です。
ロードカナロア 128ポンド
短距離路線で世界にその名を轟かせたのがロードカナロアです。特に2013年の香港スプリント連覇は圧巻で、この年の香港スプリントにおいて128ポンドのレーティングを獲得しました。日本調教馬として初めて香港スプリントを連覇するという快挙を成し遂げた、スプリンターとしての絶対的な能力を示した名馬です。
ディープインパクト 127ポンド
日本近代競馬の結晶とも称され、無敗でのクラシック三冠達成など数々の金字塔を打ち立てた国民的英雄、ディープインパクト。彼の最高レーティングの一つとして、2006年の有馬記念などが挙げられ、JRA公式ではこの有馬記念で127ポンドとされています(国際的にはこの数値で非常に高い評価を得ました)。その英雄的な走りで多くのファンを熱狂させました。
アーモンドアイ 124ポンド
最後に、G1・9勝という芝G1最多勝記録を樹立した名牝アーモンドアイです。彼女はキャリアを通じて高いパフォーマンスを維持し、ジャパンカップを2度制覇(2018年、2020年)するなど、数々の大レースで輝かしい成績を残しました。その最高レーティングは124ポンドで、2020年には牝馬として世界最高の評価を受けました。国内外の強豪牡馬とも互角以上に渡り合ったその強さは、競馬史に燦然と輝いています。
【初心者向け】レーティング数値の目安:どれくらいの強さ?
レーティングの数値だけを見ても、それが具体的にどの程度の強さを示すのか、イメージが湧きにくいかもしれません。以下に大まかな目安を示します。
この目安はあくまで大まかなものですが、馬の強さをイメージする助けになるでしょう。
競馬の「レーティング」とは?基本を徹底解説
競馬の世界で頻繁に耳にする「レーティング」という言葉。まずはその基本から丁寧に見ていきましょう。
レーティングの定義:競走馬の能力を測る「ものさし」
JRA(日本中央競馬会)の公式な説明によれば、レーティングとは「競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したもの」とされています。
JRA公式サイト レーティング&ランキング
この国際的な基準があるおかげで、日本の馬だけでなく、世界中の競走馬の能力を比較することができます。
より簡単に言えば、レーティングは「馬の強さを表す点数」のようなものです。馬がレースで見せたパフォーマンスを客観的な「点数」として数値化したもの、と考えると分かりやすいでしょう。そして、この「点数」が高ければ高いほど、その馬がそのレースで優れたパフォーマンスを発揮した、つまり「強かった」ということを意味します。
なぜレーティングが必要?その目的と重要性
では、なぜこのようなレーティングという指標が必要なのでしょうか。それにはいくつかの重要な目的があります。
- 客観的な能力比較
- 国際比較
- ハンデキャップ設定の基礎
- レースの格付け
客観的な能力比較
最大の目的は、異なるレースを走った馬同士の能力を、共通の基準で比較することです。例えば、Aというレースで勝った馬と、Bという全く別のレースで勝った馬、どちらが本当に強いのかを判断する際に、レーティングは客観的な判断材料を提供します。
国際比較
レーティングは世界共通の基準なので、日本の馬が海外のレースに出たり、海外の強い馬が日本に来たりした時に、お互いの強さを比べる目安になります。時には、世界中の馬の強さをランキング形式で発表することもあり、日本の競走馬が世界の強豪馬と比較してどの程度の位置にいるのか、といった国際的な評価を知る手がかりにもなります。
ハンデキャップ設定の基礎
ハンデキャップレースでは、出走馬の実力差を埋め、レースをより接戦にするために、各馬が背負う斤量(負担重量)が調整されます。この斤量を決定する際に、レーティングが重要な参考資料として用いられます。
レースの格付け
個々の馬だけでなく、レース自体のレベルを示す「レースレーティング」というものも存在します。これは、G1、G2、G3といったレースの格付けを維持したり、新たに格付けを審査したりするための重要な基準の一つとなります。
レーティングの単位「ポンド」の意味と由来
競走馬のレーティングは、通常「ポンド(lb)」という単位で表されます。競馬に馴染みのない方にとっては、なぜ重さの単位であるポンドが使われるのか疑問に思うかもしれません。
この「ポンド」という単位の使用は、競馬におけるハンデキャップの長い歴史と深く関連しています。元来、ハンデキャップは、強い馬に余分な「重さ」を背負わせることで、馬の実力差を調整する手法でした。この「重さ」の単位として、競馬発祥の地であるイギリスをはじめとする欧米諸国で伝統的にポンドが用いられてきたのです。
レーティングも、そのハンデキャップの考え方を系譜としており、競走馬の能力差を、もし同じレースで走った場合にどれくらいの斤量差(重さの差)に相当するか、という形で数値化する発想に基づいています。そのため、レーティングの単位にもポンドが採用されているのです。ちなみに、1ポンドは約0.45kgに相当します。
JRAレーティング詳解:日本の競馬における評価基準

日本の競馬ファンにとって最も身近なレーティングは、JRAが発表するものでしょう。このJRAレーティングがどのように決められ、どのような種類があるのかを詳しく見ていきます。
JRAレーティングはどう決まる?算出に関わる要素の概要
JRAレーティングは、専門のハンデキャッパー(格付担当者)によって、様々な要素を総合的に評価して決定されます。具体的な計算式は非常に複雑で一般には公開されていませんが、主に以下のような要素が考慮されます。
レースの格や着順、着差
G1、G2、G3といった重賞格から、オープン特別、条件戦に至るまで、出走したレースのレベルがまず考慮されます。格の高いレースで好走するほど、高い評価を得やすくなります。レースでの最終的な着順は最も基本的な評価要素であり、1着馬と2着馬、2着馬と3着馬といった上位入線馬間の着差(馬身差やタイム差)も重要です。一般的に、0.1秒または1/2馬身の差がレーティングの1ポンドに相当するとされることがあります。
対戦相手のレベルと斤量
どのようなレベルの馬たちと競い合ったかは、パフォーマンスの価値を測る上で非常に重要です。既に高いレーティングを持つ馬を相手に好走すれば、評価は高まります。また、その馬がレースで背負っていた負担重量も評価に影響します。
例えば、同じ着差であっても、より重い斤量を背負っていた馬の方が高く評価される傾向にあります。0.5kgの斤量差が1ポンドに相当するとされることもあります。
過去のレーティングも、新たなレーティングを決定する際の基準となります。
ハンデキャッパーの専門的な役割
JRAには、これらの要素を専門的に分析・評価し、レーティングを決定する「ハンデキャッパー」と呼ばれる格付担当者がいます。彼らは長年の経験と専門知識に基づき、各レースの結果を精査し、それぞれの馬に適切なレーティングを付与します。
特に、レーティングが114ポンド以下の馬については、JRAのハンデキャッパーおよびNAR(地方競馬全国協会)のレーティング担当者が協議して決定します。
一方で、非常に高いレーティング(例えば115ポンド以上)を持つトップクラスの馬については、JRAだけでなく、海外の専門家も交えた国際的な話し合いで評価が決まることもあります。
これにより、世界的に通用する客観的な評価が保たれます。
JRAレーシングの種類と分類
JRAが発表するレーティングや、それに関連するランキングにはいくつかの種類があります。
芝・ダートレーティングと距離区分(SMILEC)
競走馬は芝コースを得意とする馬もいれば、ダートコースで真価を発揮する馬もいるため、JRAでは「芝レーティング」と「ダートレーティング」を区別して評価することがあります。また、馬の能力は走る距離によっても大きく左右されるため、国際的には「SMILEC(スマイレック)区分」と呼ばれる以下のカテゴリーが用いられ、レーティングが付与される際には、そのパフォーマンスがどの距離区分のレースで発揮されたかを示す情報が付記されます。
- S (Sprint): 1000m~1300m(北米では1000m~1599m)
- M (Mile): 1301m~1899m(北米では1600m~1899m)
- I (Intermediate): 1900m~2100m
- L (Long): 2101m~2700m
- E (Extended): 2701m以上
JRAが発表する「JPNサラブレッドランキング」では、各馬のその年における最高のレーティングとともに、そのレーティングを獲得したレースの距離区分がこのSMILECコードで示されます。
JRAが発表する主なランキング(重賞競走等レーティング、JPNサラブレッドランキング等)
JRAは、ファンや関係者に向けて、いくつかの異なる形式でレーティング情報を提供しています。
| 種類 | 内容 | 発表頻度 | 主な対象 |
| 重賞競走等レーティング | G1全馬、他重賞・OP4着までの馬のレーティング | 毎週 | 当該レース出走馬 |
| GⅠ競走プレレーティング | G1特別登録馬の現時点での最高レーティング | G1レース週月曜日 | G1レース登録馬 |
| JPNサラブレッドランキング | レーティング100以上の日本馬の年間ランキング | 上半期・通年の年2回 | 日本調教馬(レーティング100以上) |
| クラシフィケーション | 年齢・芝/ダート・距離別の競走馬格付け | 年度末(例年1月発表) | JRA所属の2歳、3歳、4歳以上馬 |
| レースレーティング | レース上位4頭の公式レーティング平均値 | G1など主要レース後、年間など | G1など主要レース |
| ワールドサラブレッドランキング | 世界のトップホースのランキング(国際機関が発表) | 年間複数回、最終は翌年1月 | 世界のトップホース |
JRAレーティングの確認方法
これらのJRAレーティングや関連ランキングは、JRAの公式ウェブサイトで確認することができます。主に「データファイル」の「レーティング&ランキング」というセクションにまとめられています。

また、競馬新聞やJRAが発行するレーシングプログラム(馬柱)にも、オープンクラス以上の競走では各馬のレーティングが記載されていることがあります。
「レースレーティング」とは?レース自体のレベルを示す指標

これまで個々の競走馬の能力を示す「レーティング」について解説してきましたが、実はレースそのものにも「レースレーティング」という評価が存在します。
レースレーティングの定義と算出方法の概要
レースに出走した馬のうち、上位4着までに入った馬の公式レーティング(その馬がその年度に獲得した最高のレーティング)の平均値により「年間レースレーティング」が算出されます。この数値は、そのレースの「競走の質」、つまりどれだけレベルの高い馬たちが集まり、優れたパフォーマンスを繰り広げたかを表すものとされています。
レースの格付け(G1, G2, G3)との深い関係
レースレーティングの最も重要な役割の一つは、G1、G2、G3といったレースの国際的な格付けを審査し、その格を維持するための客観的な基準として用いられることです。この格付けは定期的に見直され、その際に過去数年間のレースレーティングの平均値が、その格にふさわしい基準を満たしているかどうかが審査されます。
例えば、古馬が出走するG1競走がその最高の格付けであるG1を維持するためには、レースレーティングがおおむね115ポンド以上であることが求められます。同様に、G2競走であれば110ポンド以上、G3競走であれば105ポンド以上といった具体的な基準値が設けられています。
もしあるレースのレースレーティングが、継続してその格付けの基準値を下回れば格下げの対象となる可能性があり、逆に格下のレースが一貫して高いレースレーティングを記録し続ければ格上げの審査対象となることもあります。国際的な競馬機関が毎年発表する「世界のトップ100 G1レース」ランキングも、この年間レースレーティングに基づいて作成されています。
では、具体的に日本の主要G1レースが、年間レースレーティングとしてどの程度のレベルで評価されているのか、いくつかの例を見てみましょう。
- ジャパンカップ
- 国際G1。世界トップクラスの馬が集う。
- 2023年: 126.75 (年間世界1位のレース)。勝ち馬は通常121~126程度。
- 有馬記念
- 国際G1。年末のグランプリ。
- 2024年発表のトップ100 G1では120.25 (20位)。勝ち馬は通常120~126程度。
- 東京優駿(日本ダービー)
- G1。3歳クラシックの頂点。世代トップクラスの能力が求められる。
- 2024年発表のトップ100 G1では118.75 (36位)。
- その他G1レース
- 国際G1格付けを維持するには、レースレーティングが概ね115ポンド以上であることが目安。
これらのレースレーティングは、その年の出走メンバーのレベルによって変動しますが、概ね高い水準で推移しています。
レーティングを競馬予想に活かす!メリットと注意点
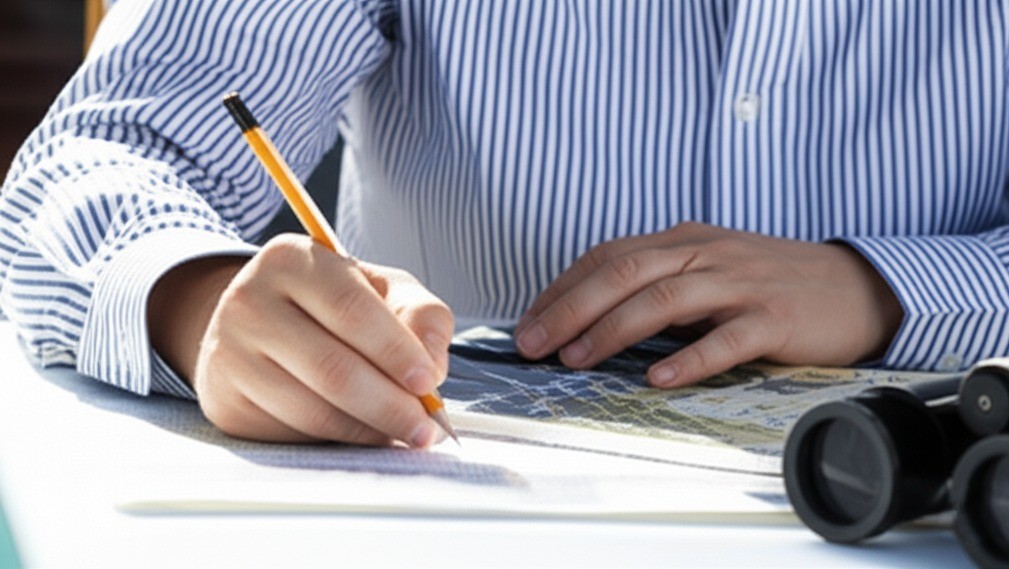
レーティングは単なる数値の羅列ではなく、競馬の様々な場面で実際に活用されています。
ハンデキャップレースにおけるレーティングの活用
ハンデキャップレースでは、出走馬の実力差を埋めるために、各馬が背負う負担重量(斤量)を調整します。この斤量を決定する上で、レーティングが非常に重要な役割を果たします。JRAのハンデキャッパーたちが、各出走予定馬のレーティング、近走の調子、距離適性などを総合的に評価し、負担重量を決定します。一般的に、レーティングが高い馬ほど重い斤量を背負わされます。
競馬のハンデ戦とは?別定戦との違いや高回収率条件の解説はこちら>>>
レーティングが出走条件になるケース(G1など)
G1レースなど、一部の格の高いレースでは、出走馬の質を一定以上に保つために、レーティングが出走条件の一つとして用いられることがあります。
レーティングを見るメリット:客観的評価と成長度の確認
レーティングという指標を理解し、活用することには多くのメリットがあります。
- 客観的な能力評価
- 応援している馬や気になる馬の強さを客観的な数値で把握できる
- 異なるレースを走った馬の比較
- 直接対決のない馬同士の力関係を推測する材料になる
- レースレベルの把握
- 出走馬全体のレーティングからレースのおおよそのレベル感を判断できる
- 成長度の確認
- 若い馬のレーティング変動から成長度を推測する手がかりになる
- 国際的な視点
- 海外挑戦馬や来日外国馬の実力を測る上で役立つ
レーティングの限界と解釈の注意点:絶対ではない指標
レーティングは非常に有用な指標ですが、万能ではありません。
- 絶対的な指標ではない:
- 馬の体調、馬場状態、展開、騎手の戦略など全てを反映するものではありません。
- 「高い=必ず勝つ」ではない:
- 勝利を保証するものではなく、不確定要素が伴います。
- 特定の条件下での評価:
- ある条件で高いレーティングでも、他条件で同様とは限りません。
- 算出の主観性:
- ハンデキャッパーの評価には、ある程度の主観的要素や解釈が含まれ得ます。
- 数字だけにとらわれない:
- パドック、調教、血統、騎手との相性など、総合的な判断が重要です。
これらの限界や注意点を踏まえた上でレーティングを活用すれば、よりバランスの取れた競馬の見方ができるようになるでしょう。
レーティングと獲得賞金は何が違うのか?
競馬初心者の方が混同しやすいのが、「獲得賞金」と「レーティング」の違いです。
- 賞金: レースで上位に入着することで獲得する金銭的な報酬です。主に勝利数やレースの格によって積み重ねられます。
- レーティング: 馬がレースで見せたパフォーマンスの「質」を数値化したものです。獲得賞金額と完全に比例するわけではありません。非常に強いメンバー構成のレースで惜敗した場合、賞金は少なくても高いレーティングが付与されることがあります。
役割の違いとして、賞金は主に経済的な成果や出走資格を示し、レーティングはより純粋な能力評価、国際的な実力比較、ハンデキャップ設定の基準などに用いられます。
よくある質問(FAQ)
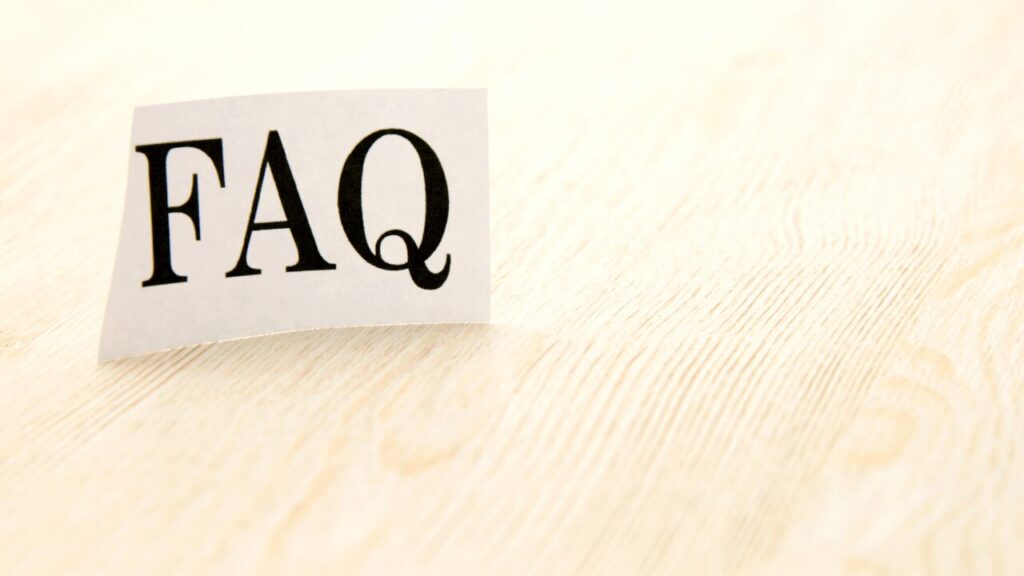
Q. レーティングが高い馬は次のレースで必ず勝ちますか?
A. いいえ、必ずしもそうではありません。レーティングは過去のパフォーマンスに基づく評価であり、馬の当日の体調、馬場状態、レース展開など多くの不確定要素がレース結果に影響します。高いレーティングは能力の証明の一つですが、勝利を保証するものではありません。
Q. JRAレーティングはどこで最新情報を確認できますか?
A. JRAの公式ウェブサイト内の「データファイル」にある「レーティング&ランキング」のページで、重賞競走等レーティング、GⅠ競走プレレーティング、JPNサラブレッドランキングなどの最新情報が確認できます。
Q. レーティング1ポンドは、斤量や着差でどれくらいに相当しますか?
A. 一般的に、0.1秒または1/2馬身の着差がレーティングの1ポンドに、また0.5kg(キログラム)の斤量差がレーティングの1ポンドに相当するとされることがありますが、これはあくまで目安です。実際のレーティング評価は、レース内容や対戦相手など様々な要素をハンデキャッパーが総合的に判断して決定します。
まとめ:レーティングを理解して競馬をもっと深く楽しもう

ここまで、競馬における「レーティング」について、その定義から種類、算出方法の概要、具体的な活用例に至るまで解説してきました。
- 馬の能力を客観的な数値で把握できる。
- レースの質そのもの(レースレーティング)に注目したり、若い馬のレーティングの推移からその成長力を測れる。
- 日本のトップホースが世界の強豪と比べてどの程度の評価を得ているのかを知ることができる。
- データに基づいた分析を加えることで、競馬の楽しみ方を広げられる。
レーティングは競馬という競技の複雑さや戦略性、そして競走馬の能力評価の一端に触れるものです。レーティングを理解することで、競馬をより深く味わうことができます。
データ分析を活用した競馬予想
様々なファクターを総合的に分析し、期待値の高い馬を見つけ出すことが、長期的な回収率向上に繋がります。
当サイトでは、今回解説したような各馬の能力も加味し、独自のデータ分析に基づいた「毎週末の中央競馬全レース無料予想」を提供しています。 あなたの競馬ライフをより豊かに、そして収支向上の一助となるような情報発信を目指していますので、ぜひ週末の予想の参考にしてみてください。