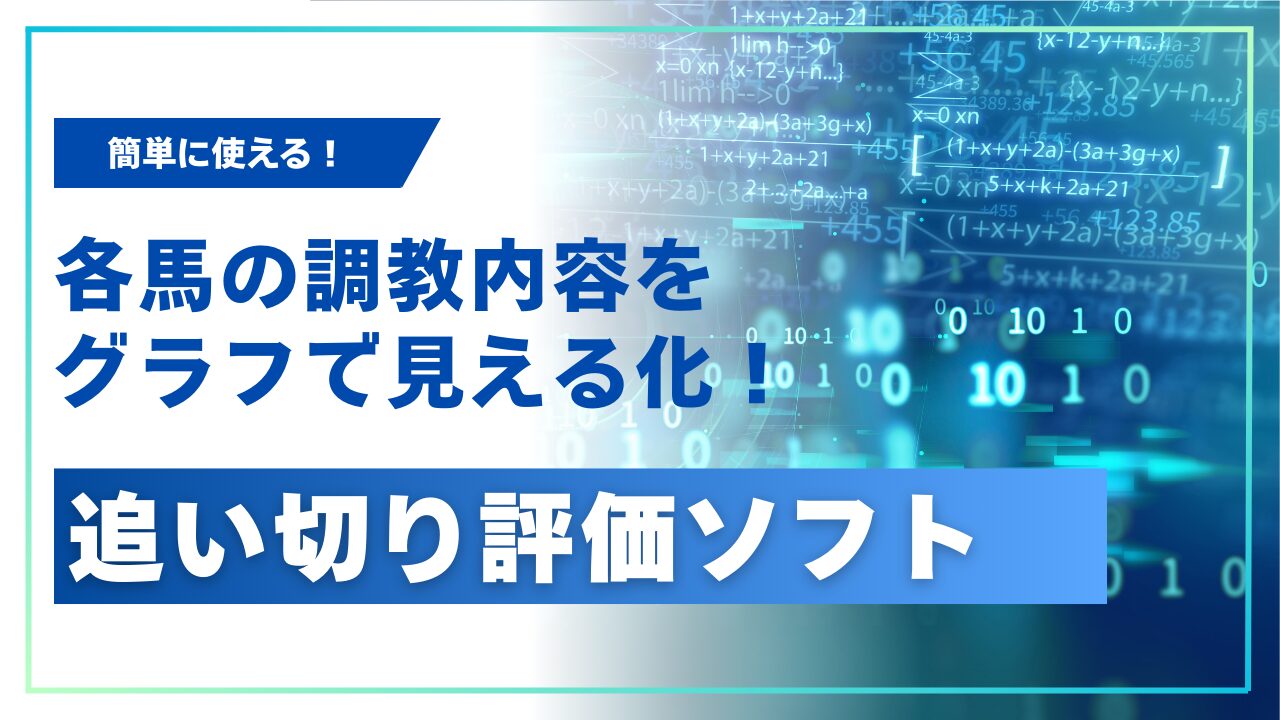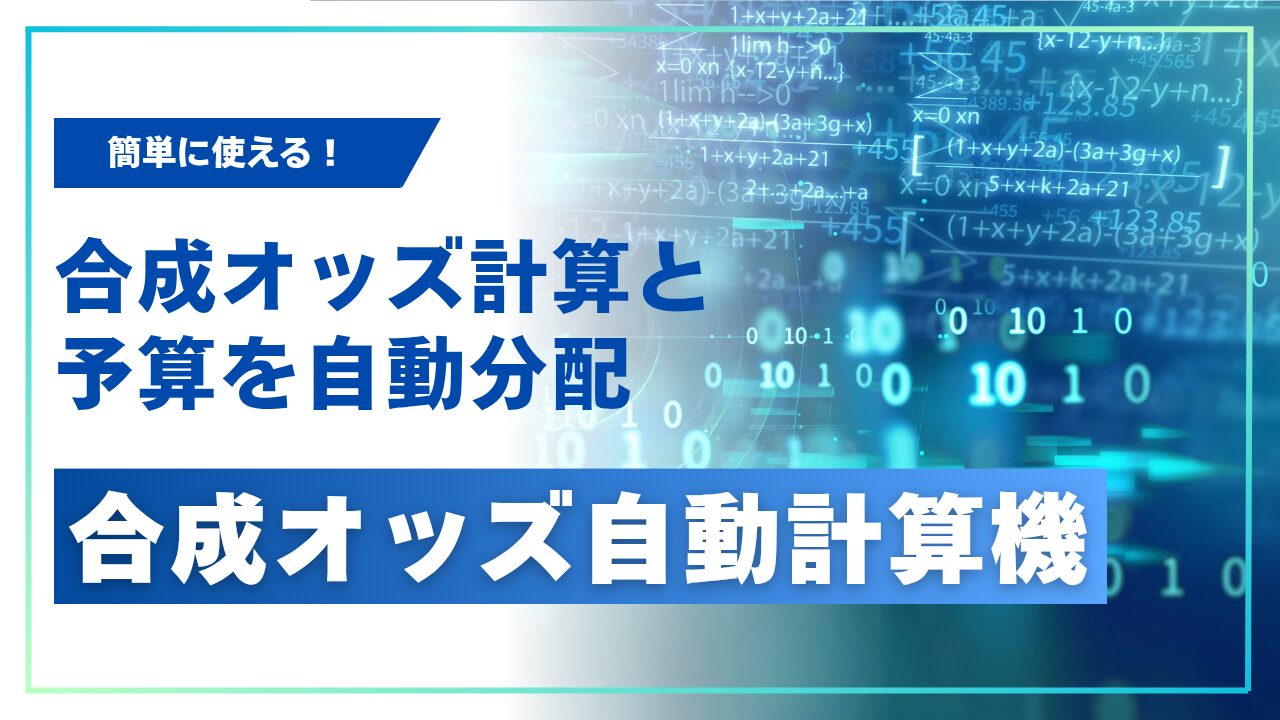【外厩とは?】競馬予想の精度を上げる!仕組み・メリット・見分け方まで徹底解説

競馬予想をしていると、「外厩」という言葉を耳にする機会は多いですよね。「ノーザンファーム天栄帰りだから買いだ!」なんて話を聞くことも。
でも、「外厩って具体的に何?」「本当に予想に役立つの?」「どうやって見分ければいいの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
この「外厩」という要素、現代競馬において予想の精度や回収率を向上させるために無視できない重要なファクターです。感覚的な予想から一歩進んで、データに基づいた論理的な予想をしたい、馬券の回収率を向上させたい、と考えているあなたにとって、外厩の知識は強力な武器になります。
しかし、単に「外厩帰りだから」という理由だけで馬券を買っても、なかなか結果には繋がりません。
この記事では、外厩の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、そして回収率向上に繋げるための具体的な活用法まで、初心者の方にも分かりやすく、かつ中級者の方にも新たな発見があるように徹底解説します。
この記事を読めば、あなたは以下のことができるようになります。
- 外厩が何であり、なぜ重要なのかを明確に理解できる。
- 外厩を利用するメリット・デメリットを把握し、予想に活かせる。
- レース情報から外厩帰りかどうかを見抜き、その情報をどう評価すべきか判断できる。
- データに基づき、外厩情報を自信を持って馬券戦略に組み込めるようになる。
外厩情報を正しく理解し、他の要素と組み合わせて分析することが、回収率向上のための重要な鍵となります。この記事で、その具体的な方法を掴んでいきましょう。
実は、休み明けの馬の成績は年々向上している?

「休み明けは割引」という言葉は、競馬ファンなら一度は耳にしたことがある格言かもしれません。しかし、近年その傾向に変化が見られることをご存知でしょうか?
当サイトで独自に調査した、2011年以降の休み明け(中14週以上)の馬の年度別複勝率データをご覧ください。
| 年度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 複勝率 | 15.5% | 14.9% | 16.1% | 16.4% | 16.7% | 16.6% | 16.9% | 18.0% | 18.6% | 17.5% | 18.7% | 19.0% | 17.7% | 18.0% |
このグラフが示すように、休み明け馬の複勝率は、2011年の15.5%から、近年では18%を超える水準まで明らかに上昇傾向にあります。
特に2018年以降は高い水準で安定しており、かつての「休み明け=割引」という考え方は、現代競馬においては必ずしも当てはまらなくなってきています。
では、なぜこのような変化が起きているのでしょうか?その大きな要因の一つとして考えられるのが、「外厩」の存在とその利用の進化です。
外厩とは? 基本的な定義と役割
まず、「外厩(がいきゅう)」とは何か、基本的なところから確認しましょう。
外厩とは、JRA(日本中央競馬会)のトレーニングセンター(美浦・栗東)の外にある、競走馬の育成・調教を行う民間の施設のことです。
これらの施設は、単なる休養場所ではなく、トレセンと同等、あるいはそれ以上の調教設備や専門スタッフを備えている場合が多く、レースに向けた調整や、放牧中の馬のコンディション維持・向上を目的として利用されます。
なぜ外厩が必要なのか? その背景
では、なぜわざわざトレセンの外にこのような施設が必要なのでしょうか? それにはいくつかの理由があります。
- トレセンの馬房数制限
- 調教技術の専門化と高度化
- 馬のリフレッシュ
トレセンの馬房数制限
JRAのトレセンには、各厩舎が管理できる馬の数(馬房数)に限りがあります。このため、全ての管理馬を常にトレセン内に置いておくことはできません。レースに出走しない馬や、休養が必要な馬は、トレセンの外に出す必要があるのです。
これにより、厩舎はより多くの管理馬に適切なケアを提供し、効率的なローテーションを組むことが可能になります。
調教技術の専門化と高度化
近年、競走馬の育成・調教技術は目覚ましく進歩しています。外厩の中には、特定の分野(例: 坂路調教、ゲート練習、心肺機能強化)に特化した設備やノウハウを持つ施設も多く、馬の状態や目的に合わせて最適な環境で調整を行うことが、強い馬作りには不可欠となっています。
例えば、特定の外厩では最新の坂路設備やゲート練習施設を活用し、馬の弱点克服や能力向上に特化したトレーニングを行うことができます。これがレースでのパフォーマンス向上に直結するケースも少なくありません。
馬のリフレッシュ
常にレースのプレッシャーに晒されるトレセンの環境から離れ、よりリラックスした環境で過ごすことは、馬の精神的なリフレッシュにも繋がります。これが、レースでのパフォーマンス向上に寄与することもあります。特に連戦で疲労が蓄積した馬や、精神的に煮詰まった馬にとって、環境を変えることは良い刺激となり、レースへの集中力を高める効果が期待できます。
外厩を利用するメリット・デメリット

外厩を利用することは、競走馬にとって、そして馬券を予想する私たちにとって、どのような影響があるのでしょうか?メリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット
外厩を利用する主なメリットは以下の通りです。
- 充実した設備での調教
- 専門スタッフによるケア
- リフレッシュ効果
- 効率的な馬房運営
- レース直前の「仕上げ」
充実した設備での調教
例えば、有名な外厩である「ノーザンファーム天栄」(福島県)や「ノーザンファームしがらき」(滋賀県)は、JRAトレセンにも匹敵する、あるいは部分的には凌駕するほどの調教施設を備えています。(坂路コース、周回コース、屋内トラック、トレッドミル、スイミングプールなど)
これにより、トレセンにいるのと同等、もしくはそれ以上の負荷をかけたトレーニングが可能になります。
専門スタッフによるケア
外厩には、獣医師や装蹄師、調教専門のスタッフなどが常駐している場合が多く、馬体のケアやコンディション管理を密に行うことができます。これにより、故障のリスクを抑えつつ、馬の能力を最大限に引き出すことが可能になります。
リフレッシュ効果
トレセンの喧騒から離れ、より落ち着いた環境で過ごすことで、馬の精神的な疲労回復や気分転換が促されます。
レース直前の「仕上げ」
特に重要なのが、この「外厩仕上げ」という考え方です。トレセンに入厩してからレースまでの期間は限られています。外厩でしっかりと乗り込み、ある程度レースで走れる状態まで仕上げてからトレセンに移動することで、トレセンではレースに向けた最終調整(追い切りなど)に集中できます。
これにより、休み明けでも仕上がり切った状態でレースに臨むことが可能になるのです。これが、「休み明けの外厩帰りは買い」と言われることがある理由の一つです。
デメリット
一方で、外厩利用には注意すべき点もあります。
- 情報入手の難しさ
- 移動による負担
- 必ずしも好結果に繋がるわけではない
- 「過剰人気」の可能性
情報入手の難しさ
トレセンでの調教時計やコメントは、競馬新聞や専門誌、JRA公式サイトなどで比較的容易に入手できますが、外厩での詳細な調教メニューや状態の変化は、関係者のコメントなど断片的な情報に限られることが多いです。そのため、外厩での状態を正確に把握するのは難しい場合があります。
移動による負担
トレセンと外厩間の輸送は、距離にもよりますが、馬にとって少なからず負担となります。輸送減り(輸送によって馬体重が減ること)や、環境変化によるストレスも考慮する必要があります。
必ずしも好結果に繋がるわけではない
当然ながら、外厩で調整されたからといって、全ての馬が好走するわけではありません。馬自身の能力やコース・距離への適性、レース展開、当日の馬場状態など、他の要因も結果を大きく左右します。
「過剰人気」の可能性
特に「ノーザンファーム天栄」や「ノーザンファームしがらき」といったトップクラスの外厩で調整された馬は、そのブランドイメージから過剰に人気を集めることがあります。回収率を重視する観点からは、このような「見えている情報」に過度に依存せず、オッズとのバランスを考慮することが重要です。
回収率向上に繋げる!外厩情報の見方と活用法
さて、ここからが本題です。外厩の知識を、どのようにして実際の馬券予想、そして回収率の向上に繋げていくか、具体的なポイントを解説します。
1. 「どこ」の外厩帰りか? 施設による特徴の違い
まず重要なのは、「どの外厩で調整されたのか?」という点です。外厩と一口に言っても、その規模、設備、得意とする調整方法、そして提携している厩舎や馬主は様々です。代表的な外厩とその特徴をいくつか挙げてみましょう。
- ノーザンファーム天栄 (福島県)
- ノーザンファームしがらき (滋賀県)
- 吉澤ステーブル (EAST/WEST)
- チャンピオンヒルズ (滋賀県)
ノーザンファーム天栄 (福島県)
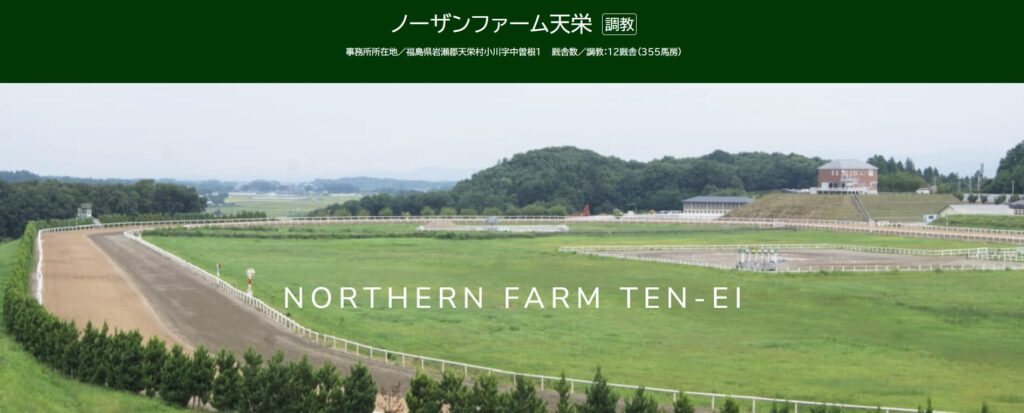
社台グループ(特にシルクレーシング、キャロットファームなど)の関東馬が多く利用する外厩です。最新鋭の設備と豊富なスタッフを擁し、「外厩仕上げ」のレベルが高いことで知られています。また、美浦トレセンへのアクセスが良い点も特徴です。
ノーザンファームしがらき (滋賀県)
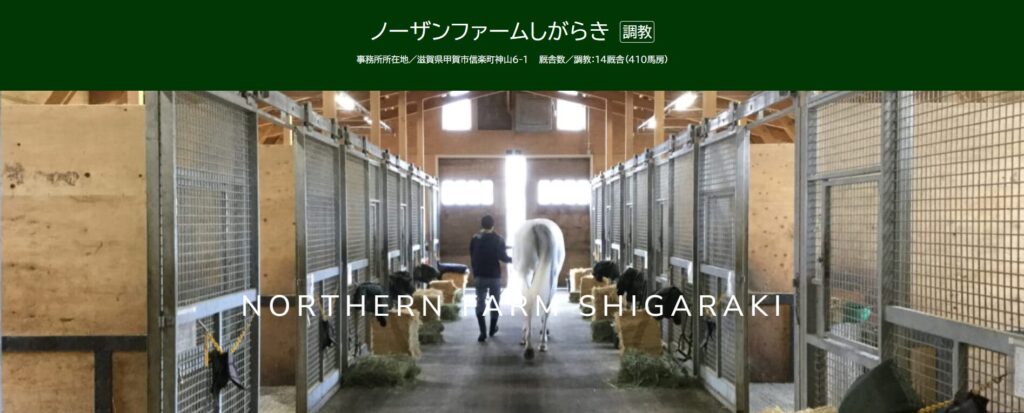
こちらは社台グループの関西馬が中心となります。天栄と同様に高水準の施設・スタッフを誇り、栗東トレセンに近い立地です。
吉澤ステーブル (EAST/WEST)

育成から中期的な滞在、短期の調整まで幅広く対応しています。坂路やトラックコースなど充実した設備を持ち、社台系以外の馬主や厩舎の利用も多いのが特徴です。
チャンピオンヒルズ (滋賀県)
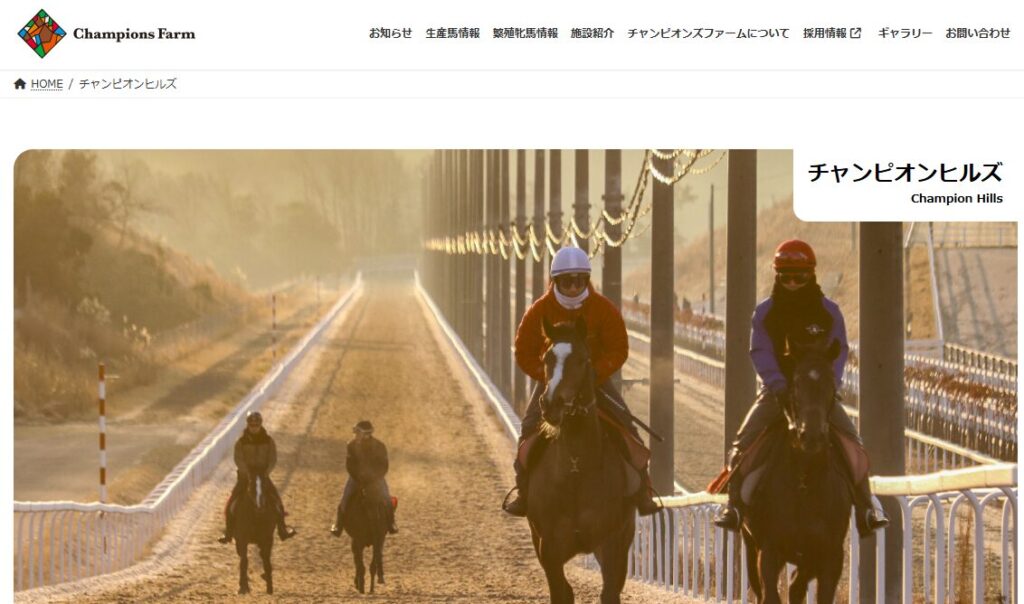
比較的新しい大規模外厩施設で、栗東近郊に位置し、多くの関西馬が利用しています。育成年代から古馬まで幅広く対応可能です。
2. 「いつ」外厩から帰ってきたか? 在厩期間とレース間隔
次に注目したいのが、「外厩からトレセンに戻ってきたタイミング」と「外厩での滞在期間」です。
- レース直前の帰厩
- 長期滞在後の帰厩
- 短い放牧からの帰厩
レース直前の帰厩
レースの1〜2週前にトレセンに戻ってくるパターンは、外厩でしっかり仕上げてきた可能性が高いと考えられます。これは、いわゆる「メイチ勝負」(そのレースに照準を合わせて最高の状態に仕上げること)のサインである可能性もあります。
長期滞在後の帰厩
数ヶ月単位で外厩にいた後のレースは、立て直しや成長を促すための期間だったと考えられます。馬がどのように変わったか、トレセンでの追い切りや馬体、パドックでの気配などを慎重に見極める必要があります。大幅な成長が見られることもあれば、まだ本調子でない場合もあります。
短い放牧からの帰厩
レース後、短期(数週間程度)だけ外厩でリフレッシュしてすぐにトレセンに戻ってくる場合もあります。これは疲労回復が主目的と考えられますが、リフレッシュ効果で馬が上向いている可能性もあり、油断は禁物です。
3. トレセンでの「最終確認」を怠らない

外厩情報はあくまで有力なヒントの一つであり、それだけで馬券の判断を下すのは早計です。最も重要なのは、トレセン入厩後の状態です。
- 追い切り
- 馬体重
- パドック
- 厩舎コメント
追い切り
外厩でしっかり乗り込んできた馬は、トレセンでの追い切り本数が少なくても、時計や動きが良ければ仕上がっていると判断できます。逆に、外厩帰りでも動きが重かったり、時計が平凡だったりする場合は割引が必要です。
馬体重
休み明けの外厩帰りでは、馬体重の大幅な増減に注意が必要です。特にプラス体重が大きすぎる場合は、まだ絞り切れていない(仕上がり途上)可能性があります。逆に、マイナス体重が大きい場合は、輸送や調整過程で消耗している可能性も考えられます。
パドック
レース直前のパドックでの気配(落ち着き、適度な発汗、力強い歩様、毛ヅヤなど)は、その馬の当日のコンディションを知る上で非常に重要です。外厩での評価が高くても、当日の気配が悪ければ見送る勇気も必要です。
【パドックの見方をマスター】競走馬の状態を見抜くポイントを徹底解説!>>>
厩舎コメント
調教師や厩舎スタッフのコメントも参考にしましょう。「外厩で順調に乗り込めた」「まだ良くなる余地がある」「今回は試走の意味合いが強い」など、陣営のトーンを確認します。ただし、コメントは必ずしも本音とは限らないため、他の情報と合わせて判断することが重要です。
4. データ分析で「外厩効果」を客観的に評価する
感覚だけでなく、データに基づいて外厩の効果を評価することも重要です。
- 外厩別成績
- 厩舎×外厩の組み合わせ
- 休み明け成績
外厩別成績
特定の外厩を利用した馬の、コース別、距離別、クラス別などの成績データを分析します。得意な条件、苦手な条件が見えてくることがあります。
厩舎×外厩の組み合わせ
特定の厩舎と外厩の組み合わせの成績を分析します。厩舎と外厩の連携の強さや、調整方針の相性などにより、特定の組み合わせで好成績を収める傾向が存在する可能性があります。
休み明け成績
外厩を利用した休み明け(放牧明け)の成績と、利用しなかった場合の成績を比較します。これにより、その外厩が休み明けの仕上げにどれだけ効果を発揮しているかを客観的に評価できます。
まとめ:外厩情報を武器に、一歩先の競馬予想へ

今回は、現代競馬でますます重要度を増している「外厩」について、基本的な知識から実践的な活用法まで解説しました。
外厩とは
トレセン外にある民間の育成・調教施設です。馬房数制限や調教技術の高度化を背景に利用が拡大しています。
メリット
充実した設備での調教、専門スタッフによるケア、リフレッシュ効果、効率的な馬房運営、レース直前の「仕上げ」が可能になる点などが挙げられます。
デメリット
情報入手の難しさ、移動による負担、必ずしも好結果に繋がらないこと、過剰人気の可能性などには注意が必要です。
活用法
以下の点をチェックし、総合的に判断することが重要です。
- 「どこ」の外厩か: 施設ごとの特徴を把握します。
- 「いつ」帰厩したか: 在厩期間とレース間隔に注目します。
- トレセンでの「最終確認」: 追い切り、馬体重、パドック、コメントなどを必ず確認します。
- 「データ分析」: 客観的な評価のためにデータを活用します。
外厩情報は、正しく理解し活用すれば、あなたの競馬予想の精度を格段に向上させる可能性を秘めています。
しかし、「〇〇外厩帰りだから」という短絡的な思考ではなく、なぜその外厩が使われたのか、外厩でどのような調整が行われたと推測されるのか、そしてトレセンでの最終的な状態はどうなのか、という一歩踏み込んだ分析を心がけることが重要です。
データ分析を活用した競馬予想
外厩情報を含む様々なファクターを総合的に分析し、期待値の高い馬を見つけ出すことが、長期的な回収率向上に繋がります。
当サイトでは、今回解説したような外厩情報も加味し、独自のデータ分析に基づいた「毎週末の中央競馬全レース無料予想」を提供しています。 あなたの競馬ライフをより豊かに、そして収支向上の一助となるような情報発信を目指していますので、ぜひ週末の予想の参考にしてみてください。